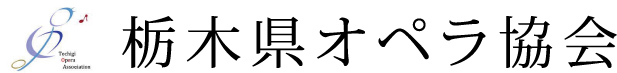

いつも栃木県オペラ協会の活動にご理解、ご支援をいただき、ありがとうございます。
この度、「オペラよもやま話」のコーナーを開設することになりました。このコーナーでは、栃木県オペラ協会が公演するオペラについての解説やその作曲家についてのエピソード、楽屋ばなし等オペラにさらに興味をもっていただけるような内容を掲載していく予定です。不定期になるとは思いますが、このコーナーが皆様のオペラ鑑賞の一助になれば幸いです。
第2回 メルヘンオペラの作曲家 エンゲルベルト・フンパーディンク

栃木県オペラ協会では、教育団体様のご支援をいただき、毎年『いきいき音楽体験事業』を実施しております。この事業では、県内の小、中、特別支援学校を訪問し、フンパーディンク作曲 オペラ『ヘンゼルとグレーテル』の公演を行っております。今年度(令和4年度)も10月に6校で実施する予定です。
情報化社会と言われ、日常生活の中に音楽が溢れている現在でも地方では子供たちが生のオペラを鑑賞する機会は滅多にありません。学校でオペラを公演することは、子供たちにオペラを知って体験してもらう大変良い機会だと思います。実際、これまで公演した学校にも大変好評をいただいております。(この事業の詳細につきましては、当ホームページの『活動のご案内』をご覧ください。)
さて、「オペラよもやま話」第2回は、このエンゲルベルト・フンパーディンク作曲『ヘンゼルとグレーテル』を取り上げます。

〇フンパーディンクはどんな人
ドイツの作曲家エンゲルベルト・フンパーディンクは、1854年にドイツ西部ライラント地方のジークブルクに生まれました。日本では江戸時代(幕末)で、ちょうどこの年アメリカとの間で「日米和親条約」が結ばれています。
ケルン音楽院で学んだ後、奨学金を得てミュンヘンやイタリアでも研鑽を積んでいます。そのイタリア留学中にリヒャルト・ワーグナーの知遇を得てバイロイトに招かれ、楽劇『パルジファル』の上演を補佐したりもしています。その後は、フランクフルトやベルリンの音楽院で作曲の教授を務めています。
彼の作品には、合唱曲や管弦楽曲、そしていくつかのオペラ等がありますが今日では『ヘンゼルとグレーテル』のみが有名です。因みに『ヘンゼルとグレーテル』はメルヘンオペラとよばれていますが、メルヘンオペラとは、おとぎ話や民話、童話を基にした台本に作曲されたオペラのことです。そして当時、ヨーロッパの音楽界を席捲していた理論的なワーグナーの楽劇に対して、もっと親しみやすい音楽を求めていた大衆に支持されていきました。なお、『ヘンゼルとグレーテル』の台本はフン
パーディンクの妹アーデルハイト・ヴェッヘの手によるものです。

〇グリム兄弟により7回も改訂された「グリム童話集」
皆さんご存知のように、『ヘンゼルとグレーテル』は「グリム童話集」の中の有名なお話です。誰でも子どものころ一度は読んだり読み聞かせてもらったりしたことがあると思います。
「グリム童話集」は創作された物語ではなく、19世紀にドイツで活躍した民間伝承と言語学の研究者『グリム兄弟』によって収集、編纂されたものです。ところで、『童話』という言葉を日本で初めて使ったのは、江戸時代の戯作者「山東京伝」だそうですが、ドイツ語の「メルヘン」は、必ずしも子供向けの昔話を指すものではなかったようです。(因みに『童話』に当たるドイツ語は、『キンドル・メルヘン』です。)
「グリム童話集」が最初に世に出たとき(1812年)の原題は『子供と家庭のための昔話集』で、『キンドル・メルヘン』と『ハウス・メルヘン』が合体したものでした。それゆえ初版の「グリム童話集」にはその土地や秩序に根ざして生きてきた人々の生々しい現実やアクの強い知恵などが語られており、そして、その中には中世の人々の息遣いや残酷、性愛、狂気、戦慄、知恵などが込められていたのです。
グリム兄弟がこのような童話集を編纂したのは、「大自然そのものの中にこそ道徳の源泉があり、凡愚の存在や悪人の存在も善用活用すべき」という考えが根強くあったからです。しかし、この昔話集が人々に読まれるようになるにつれ、親や批評家たちから批判を浴び、内容を子供向けに変更せざるを得ませんでした。結果7回の改訂を経て現在の形(童話201・児童のための聖書物語10)に落ち着きました。なお、7回にわたって様々な書き替えや書き加えを行ったことにより、「グリム童話集」は、もはや口承文芸とは呼べないという議論もありました。

〇『ヘンゼルとグレーテル』の物語の本質
さて、その『ヘンゼルとグレーテル』のお話ですが、本質は『子捨て』にあります。『姥捨て』や『子捨て』の物語はドイツに限ったことではなく、世界中の伝説や昔話に見られます。日本でも
東北地方などに『姥捨て山伝説』があったり、『わらす河原』など『子捨て』が行われていたと言われる地名などが残っていたりします。ではここで、『ヘンゼルとグレーテル』の初版の粗筋を見てみましょう。
《むかし、貧しい木こりの家の子どもにヘンゼルとグレーテルという兄妹がおりました。その年の飢饉で2人の家は毎日のパンにも事欠くようになり、両親はついに兄妹を森に捨てる相談をします。父親は反対しますが、心の冷たい母親に押し切られてしまいます。ヘンゼルの機転によって一度は無事に家に戻れた2人でしたが、両親はあきらめず、とうとう2人はそれまで行ったことのない森の奥深くに捨てられてしまいます。2人は森をさまよい、たどりついたお菓子の家に住む魔女に捕えられてしまいます。ヘンゼルは魔女に食べられそうになりますが、今度はグレーテルの機転で魔女を竈に押し込み、魔女は焼け死んでしまいます。2人は、魔女の家にあった真珠や宝石をポケットに詰められるだけ詰め込んで無事に家に戻り、その後は幸せに暮らします。》
初版から第3版までは2人の母親は実母になっていますが、第4版以降は継母に変えられています。しかも、お菓子の家から2人が無事に戻ると、継母はすでに亡くなっています。これは何となく魔女と継母が同一人物ではないかと想像できなくもありません。この変更は前段でも述べましたが、子供たちを厄介払いしようと夫をたきつける悪女が実の母親では教育的ではないという批判があったからと思われます。この変更によって『魔女は母親の悪魔的な面の象徴』というイメージが強くなったのは確かです。
しかし、やはりこのお話の本質は『子捨て』です。『子捨て』が行われた原因は『飢饉』です。当時の飢饉は、現代人が想像する以上に人々の心を凍らせる災害だったのです。生き残るためには道徳など捨てざるを得ません。真っ先に犠牲になったのは、老人や子どもでした。ヘンゼルとグレーテルの両親は子どもを捨てる鬼のような存在と思われるかもしれませんが、当時はどこの家でも同じようなことが行われていたのです。「衣食足りて礼節を知る」と言いますが、このような残酷な現実も『グリム童話集』では描かれていたのです。
〇オペラ『ヘンゼルとグレーテル』誕生の経緯
ここまで『グリム童話集』の成立について見てきましたが、話をオペラに戻しましょう。
フンパーディンクが『ヘンゼルとグレーテル』をオペラ化しようと思ったのは、彼の妹(アーデルハイト・ヴェッテ)のあるお願いがきっかけでした。ヴェッテは、彼女の夫の誕生祝いに『グリム童話』をやさしくして子どもたちに家庭劇を上演させようと考え、作曲家の兄にその子どもの歌を作曲してほしいと依頼したのです。彼はこの家庭劇のために4曲作曲し、実際に家族の前で上演されたときは好評を博したと言われています。
フンパーディンクはこの素材に大変興味をもち、逆に妹ヴェッテに台本の書き直しを依頼しました。その台本を基に作曲されたのが、このオペラ『ヘンゼルとグレーテル』です。
それでは、このオペラの台本は『グリム童話集』の原型とどう違っていたのでしょうか。まず、木こりの夫婦が優しいほうき作りの夫婦に変わり、そして『グリム童話』には出てこない「眠りの精」や「暁の精」、それに魔女の魔法によって姿を変えられている子どもたち、14人の天使などが加わっています。そして、子どもたちが両親と一緒に神様を讃えて終わるというフィナーレになっています。では、オペラの粗筋も見てみましょう。
《むかし、優しいほうき作り職人夫婦の子どもにヘンゼルとグレーテルという兄妹がおりました。ある日、2人は母親のいいつけで森の中に野いちごを摘みに出かけます。仲のよい2人が森の中で遊んでいるうちに、いつの間にかあたりはすっかり日が暮れてしまいます。ヘンゼルとグレーテルは怖くなって抱き合っていると、あたりに立ちこめた霧の中からかわいい小人や美しい眠りの精が姿を現します。すっかりくたびれた2人は、いつの間にか眠りの精のふりまく砂ですやすやと眠ってしまいます。やがて目をさました2人は、お菓子の家を見つけますが、ヘンゼルは魔女の魔法で閉じ込められてしまいます。しかし、魔女の呪文をすっかり覚えてしまった利口なグレーテルは、密かにヘンゼルにかけられた魔法を解き、2人は力を合わせて魔女を竈の中に押し込みます。竈は大音響とともに爆発、魔女の魔法が解けた村の子どもたちも自由になり、2人を取り囲んで喜び合います。そこへ、ヘンゼルとグレーテルの安否を気づかってやってきた両親が現れ、子どもたちは魔女が竈の中で焼けてできた大きなお菓子を持って登場、全員で神を讃える歌をにぎやかに歌って幕となります。》
このオペラは1891年から1892年にかけてフランクフルトで作曲され、1893年12月23日にワイマールにて初演されています。因みに初演の指揮者は当時29歳だったリヒャルト・シュトラウスでした。
ご覧のように、台本は『グリム童話』の原型とは大きく違っていますが、フンパーディンクの美しくも格調の高い音楽とともに大衆に愛され、今でもヨーロッパではクリスマス時期にこのオペラが子どもたちやその家族のために上演され続けています。
〇オペラを観た子どもたちの感想から思うこと




オペラ『ヘンゼルとグレーテル』を鑑賞した児童・生徒の皆さんから、上記のような絵や感想などたくさんのお手紙をいただきました。ありがとうございます。
子どもたちの感想の中で一番多かったのが、「歌い手の声を生で聴いた驚き」でした。これは、正に生演奏でしか味わえない感動だと思います。私たちは、これからも県内の多くの子どもたちにこのような感動を伝えられるように頑張っていきたいと思います。
ところで、子どものための音楽作品といえば、管弦楽曲だとブリテン作曲『青少年のための管弦楽入門』やプロコフィエフ作曲『ピーターと狼』、サンサーンス作曲『動物の謝肉祭』などがありますが、オペラとなると数は限られます。そもそもオペラの題材となる物語は、昔から男女の恋愛や悲劇を扱ったものが多く、例えばビゼー作曲の『カルメン』は、前奏曲は子どもたちに大変人気がありますが、オペラとして鑑賞させるには、やはり最後のシーンを含めて教育的に問題があります。最近ではモーツァルトの『魔笛』を子ども向けに優しくして上演する試みもなされていますが、『魔笛』の物語も子どもには理解が難しいところがあります。
音楽に限らず、芸術文化を発展させていくためには、今ではなく、未来を担う子どもたちに投資することが必要だと思います。それはすなわち、子どもたちに文化的な感動をたくさん与えることに他なりません。そのためには質の高い作品が必要です。そのような意味で、現代の作曲家にはぜひ子どものための作品を産み出してほしいと願っています。
次回、第3回は、子どもたちが感動してくれた「声」とオペラとの関係について考えてみたいと思います。どうぞお楽しみに。
文:S.O
参考文献
・初版グリム童話集1 吉原高志・吉原素子 訳 白水ブックス
・完訳グリム童話集(1) 金田鬼一 訳 岩波文庫
・完訳グリム童話Ⅰ 関 敬吾・川端豊彦 訳 角川文庫
・大人もぞっとする初版『グリム童話』 由良弥生 著 王様文庫(三笠書房)
第1回 愛と悲劇の達人「プッチーニ」

さて第1回目は、本年(2022年)6月4日(土)に宇都宮市文化会館小ホールで公演いたしました「ジャンニ・スキッキ」の作曲者「プッチーニ」です。
皆さんは上のプッチーニの写真から彼がどんな人物だと想像されますか?私見ですが、彼は今風に言えばなかなかのイケメンですし、服装を見てもすごくオシャレで、当時のご婦人方にもずいぶんもてたのではないでしょうか?
ところで、作曲家の人柄が、必ずしもその作品の内容に反映されるわけではないということはよくある話で、モーツァルトなどはその典型ではないでしょうか。私が小学校の教員だった頃、鑑賞の時間にモーツァルトの曲を聴かせるときは、彼の人となりをどう子どもたちに説明したらよいか、いつも困ったものでした。そのくらいモーツァルトの私生活には問題がありました。短命だったのもうなずけます。
しかし、別の見方をすれば、天才とはそもそもそんなものなのかもしれません。人間性としては?でも、今日まで誰も真似できなかった普遍的な美しい曲を生み出したことを考えれば、トータルとしてはバランスがとれていたと言えないでしょうか。むしろ、はたから見たら非常識なモーツァルトの特性が、あのような作品を生み出すためには必要だったと言ったら言い過ぎでしょうか?皆さんはどう思われますか?
では、プッチーニの場合はどうだったのでしょう?
〇プッチーニの本名が長いわけ

プッチーニは、1858年12月22日にイタリアトスカーナ地方「ルッカ」に生まれました。ルッカは、周囲4㎞を城壁で囲まれた城塞都市で、斜塔で有名なピサの近くの町だそうです。日本では江戸幕末時代にあたり、ちょうどこの年にアメリカのハリスとの間で日米修好通商条約が結ばれました。
ところで、プッチーニの本名は、
ジャコモ・アントニオ・ドメニコ・ミケーレ・セコンド・マリア・プッチーニ
といいます。何とも長い名前ですが、これは、宗教音楽家として名を馳せたプッチーニ一族の代々の当主の名前を受け継いだものです。西洋の名家ではよくあることで、ジャコモは、そのプッチーニ家の五代目ということになります。因みに大バッハ一族は音楽家として七代続きましたので、ヨーロッパではそれに次ぐ名門の出ということになります。
〇どうしてオペラ作曲家になったの?
プッチーニ家は、代々町の教会のオルガニストを務めたり教会のために作曲したりと、宗教音楽家として活躍してきました。ジャコモもその後を継ぐつもりだったのでしょうが、修業時代の彼はあまり勤勉な学生ではなく、まだ音楽の才能も開花していなかったようです。転機が訪れたのは18歳のとき、ヴェルディのオペラ「アイーダ」を観たことがきっかけで、本気でオペラ作曲家を目指すようになりました。
〇他のイタリアオペラの作曲家よりも作品が少ないのはなぜ?
プッチーニは1884年に最初のオペラ「妖精ヴィルリ」を発表してから最後の「トゥーランドット」が未完のまま世を去るまでの40年間にオペラを12曲(三部作を1曲と考えれば10曲)作曲しています。これは、他のイタリアオペラの作曲家の中でも少ない方です。ちなみに、ドニゼッティは30年間に七十数曲、ロッシーニは17年間に36曲、そしてヴェルディは23年間に22曲作曲しています。これは、プッチーニが題材と台本の選択に慎重のあまり、作曲するまでに時間がかかったためと言われています。彼は何人かの台本作家と組んでいましたが、台本の内容についてよく彼らとぶつかっていたようです。しかし、そのことが幸いし、プッチーニの作品はいずれも名作ぞろいで駄作がなく、当時の観客にも人気が高かったようです。プッチーニは、オペラにとって台本がいかに重要であるかをよく知っていました。
〇プッチーニの性格や私生活は?

いよいよプッチーニの本質に迫っていきましょう。
彼は「新しいもの好き」なところがあって、当時としてはまだ珍しかったモーターボートやガソリン自動車(生涯に自動車14台、モーターボート5台)を所有していました。しかしそれが災いし、1903年には自動車事故を起こし、そのせいで足を引きずるようになってしまいました。一方、服装についても流行に敏感で、たいへんオシャレだったようです。
「新しいもの好き」は彼の作品にも生かされ、彼は常に新しい音楽を研究し、その長所を自分の作品に取り入れることを忘れませんでした。例えば、「蝶々夫人」で五音音階や全音音階を効果的に取り入れて作品のエキゾチックな面を強調したり、ワーグナーの生み出したライトモチーフを自分の作品に取り入れたりしました。
しかし、最先端の技法をさりげなく取り入れながらも、彼の音楽からイタリアらしい抒情性が失われることは決してありませんでした。彼の言葉に次のようなものがあります。
「私は聴衆に一歩先んじても数歩は先んじない。」
台本についての考え方もそうですが、彼は劇場や聴衆をよく知っており、イタリアオペラの伝統を大切に守ってきた作曲家でした。
さて、ここでプッチーニの女性関係を見ておきましょう。下世話な話になりますが、プッチーニは女好きな人だったようです。結婚生活のスタートにしてからが駆け落ちで、26歳のときに24歳のエルヴィーラと熱愛して同棲を始めましたが、彼女は人妻で、すでに2児の母でもありました。1903年に彼女の夫が死んで、翌年ようやく入籍したものの、「プッチーニの女好き」は、もはや世評となっていました。
さらに1909年に「ドーリア・マンフレーディ事件」が起こります。妻のエルヴィーラは嫉妬深い性格だったらしく、プッチーニと女中ドーリアの浮気を疑って、その女中を責め立てるようになりました。嫌がらせは大きくなっていき、ついに女中は自殺をしてしまいます。実際には、プッチーニはこの時の女中とは不倫関係になかったようですが、この事件は社会を騒がせました。
このような女性関係や女性観は、やはり彼の作品に大きな影響を及ぼしています。ミミ(ボ・エーム)やトスカ、蝶々さん(蝶々夫人)そしてリュー(トゥーランドット)など、彼の作品に登場する女性は、すべて真摯で情熱的な愛に生き、最期は悲劇的な結末を迎えています。
たとえ事故を起こそうとも最新の車に乗り続け、浮気もやめない。それがプッチーニの音楽に新しさと抒情性をもたらしたと言えるのではないでしょうか。モーツァルト同様、彼も天才の一人だったと私は思います。
〇「ジャンニ・スキッキ」について

最後は「ジャンニ・スキッキ」についてです。
このオペラは、1幕物の三部作の一つとして1900年頃から構想され、1918年に作曲が完成しています。三部作の構想は、ダンテの「神曲-地獄変・煉獄編・天国編」からヒントを得たものと言われています。当時イタ
リアではヴェリズモオペラがオペラ界を席捲しており、マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」やレオンカヴァッロの「道化師」にも影響を受けたものと考えられます。
1作目の「外套」(ヴェリズモ風の愛憎劇)は、1916年に完成していましたが、残りの2作については台本選びが難航したようです。それを救ったのは、ジョヴァッキーノ・フォルツァーノが書き下ろした「修道女アンジェリカ」(女性しか出演しない抒情劇)と「ジャンニ・スキッキ」(13世紀末のフィレンツェを舞台にした喜劇)でした。プッチーニは、アンジェリカの女性像と「ジャンニ・スキッキ」の喜劇性を大変気に入り、作曲の筆も大いに進みました。しかし、第1次大戦下で歌手が揃わず、初演はアメリカニューヨークのメトロポリタン歌劇場で行われました。しかも、プッチーニ自身初演に立ち会うことができなかったということです。
初演ではプッチーニの予想に反して「ジャンニ・スキッキ」のみが評判になりました。(彼が愛していた作品は、「修道女アンジェリカ」でした。やはり女性に興味があったのでしょうか?)そしてこの三作はそれ以後、別々に上演されることが多くなりました。
今回の私たちの公演も、「ジャンニ・スキッキ」のみの上演でした。このオペラはプッチーニ唯一の喜劇で、上演時間1時間ほどの短い作品ですが、群像劇でもあるので出演者は一部を除いてほとんど舞台に出ずっぱりで、歌唱力はもちろん高い演技力も要求されます。しかも、原語(イタリア語)上演だったので、言葉を覚えるのも一苦労です。6月の公演のために、2月から練習を積み重ねてまいりましたが、本番のできはいかがだったでしょうか?お楽しみいただけましたら幸いです。

次回、第2回はフンパーディンク作曲「ヘンゼルとグレーテル」を特集したいと思います。お楽しみに。
文 S.O
参考 南條年章 著 作曲家◎人と作品シリーズ「プッチーニ」 音楽之友社
武石英夫 著 「プッチーニのオペラ」 音楽の友・別冊「イタリア・オペラ」より
香原斗志 著 プッチーニの三つの偏執 https://www.tokyo-harusai.com/harusai_journal/puccini-1